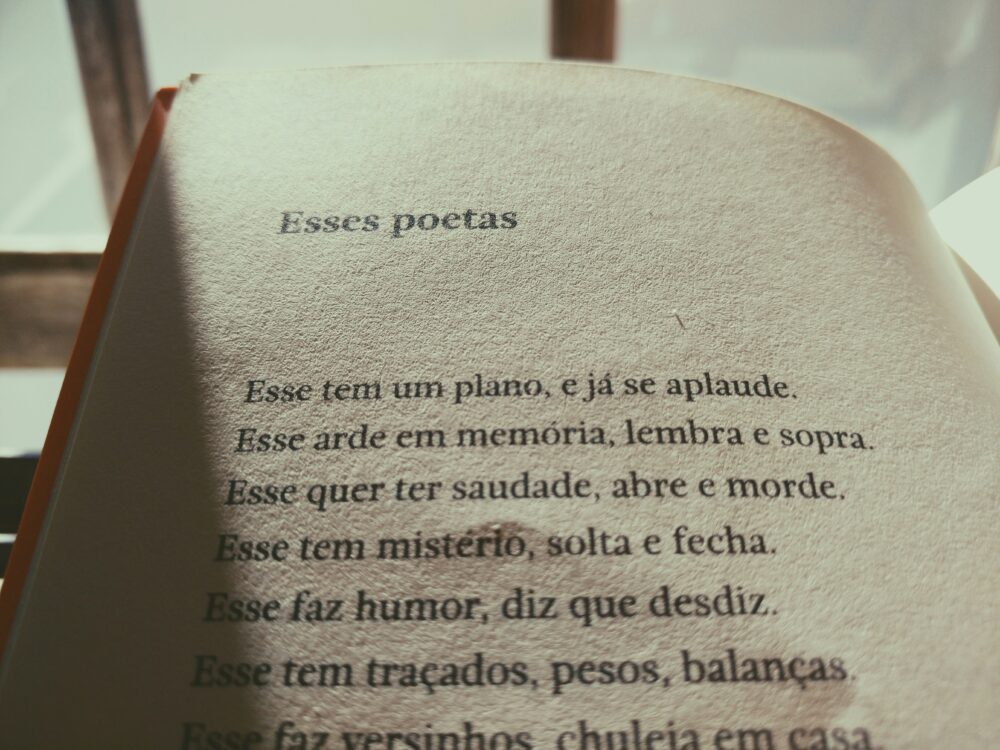はじめに
萩原朔太郎(はぎわら さくたろう)は、日本近代詩の礎を築いた詩人として広く知られ、多くの名作を通じて強烈な印象を残しています。彼の詩は、幻想的でありながらも深い感情を込めた表現が特徴であり、読む人々の心を捉え続けています。『月に吠える』『青猫』(あおねこ)『猫町』(ねこまち)などの代表作では、日常の風景や内面の葛藤を独特な言葉で描き、新しい詩のスタイルを確立しました。朔太郎の作品は、現代でも多くの人々に愛され、彼の感性は詩の世界に新たな地平を切り開いています。
この記事では、萩原朔太郎の代表作とその魅力について詳しく解説します。『月に吠える』『青猫』などの作品に焦点を当て、彼の詩の世界を探りつつ、朔太郎の詩がいかにして新しい表現を生み出したかを考察します。また、室生犀星(むろう さいせい)との関係、関連する賞についても紹介し、彼の詩の魅力と遺産がどのように現代に受け継がれているかを見ていきます。ぜひ最後までご覧ください。
萩原朔太郎とは?
萩原朔太郎の生涯と特徴
萩原朔太郎は、1886年に群馬県前橋市で生まれました。朔太郎は、1900年代初頭の日本の詩壇において、口語自由詩という新しい形式を広めた詩人の一人として知られています。彼の詩は、それまでの文語体の形式から脱却し、日常の言葉で自由に感情を表現するスタイルを確立しました。
朔太郎の詩は、内面的な感情や孤独、寂しさをテーマにすることが多く、その独特の世界観が彼の作品の特徴です。彼の詩は、しばしば幻想的でありながらも現実的な感情に根ざしており、読む人々に強い共感を呼び起こします。また、朔太郎は詩の中で、動物や自然、都市の風景などを通して人間の存在や感情を描き出すことに長けており、その表現力は多くの後進の詩人たちに影響を与えました。
朔太郎の性格は、繊細で内向的であったと言われています。友人には同じく詩人の室生犀星や北原白秋(きたはら はくしゅう)などがおり、彼らとの交流は朔太郎の詩作にも大きな影響を与えました。彼は詩を通して自己の内面を探求し続け、心の葛藤や苦悩を詩の中で表現しました。そのため、彼の詩は単なる美しい言葉の集まりではなく、深い感情と人間的な苦悩が滲み出た作品となっています。
1942(昭和17 )年5月11日に東京の自宅で亡くなりました。死因は肺炎です。
次のセクションでは、萩原朔太郎の代表作について詳しく見ていきます。『月に吠える』や『青猫』、『猫町』など、彼の名作がどのような内容であり、どのような評価を受けているのかを解説します。
萩原朔太郎の代表作
『月に吠える』
萩原朔太郎の代表作『月に吠える』は、1917(大正6)年に発表された詩集であり、彼の名を広く知らしめた作品です。この詩集は、萩原の詩作の中で初期の代表作とされ、日本の近代詩において重要な地位を占めています。『月に吠える』では、内面の孤独や絶望、都市生活の疎外感がテーマとして描かれており、萩原の独特な感性と表現が詰まっており個人的にも好きな詩です。
この詩集に収録された詩の多くは、口語体の自由詩であり、詩の形式にとらわれない感情の自由な表現が特徴です。詩の中には、萩原が感じた社会への違和感や、心の中に潜む不安感が反映され、その生々しさと詩的な美しさが読者の心を揺さぶります。タイトルの「月に吠える」という表現は、萩原自身の心の叫びを象徴しており、現実と対峙する自分の姿を描いています。
たとえば、詩『悲しい月夜』では、夜の静寂の中で孤独に吠える犬の姿が描かれています。この犬は、萩原の孤独な感情が投影されたものであり、月に向かって吠える姿は、現実と幻想が入り混じる詩人の内面的な世界を表現しています。
ぬすつと犬めが、
くさつた波止場の月に吠えてゐる。
たましひが耳をすますと、
陰気くさい声をして、
黄いろい娘たちが合唱してゐる、
合唱してゐる、
波止場のくらい石垣で。いつも、
なぜおれはこれなんだ、
犬よ、
青白いふしあはせの犬よ。──『悲しい月夜』
さらに『見しらぬ犬』という詩では、見知らぬ犬が萩原を追い続ける描写があり、その姿は萩原の孤独感と疎外感を強調しています。この犬は萩原の内なる不安や孤独の象徴であり、どこへ行ってもついてくるその姿は、彼の逃れられない運命を表現しています。
この見もしらぬ犬が私のあとをついてくる、
みすぼらしい、後足でびつこをひいてゐる不具の犬のかげだ。ああ、わたしはどこへ行くのか知らない、
わたしのゆく道路の方角では、
長屋の家根がべらべらと風にふかれてゐる、
道ばたの陰気な空地では、
ひからびた草の葉つぱがしなしなとほそくうごいて居る。ああ、わたしはどこへ行くのか知らない、
おほきな、いきもののやうな月が、ぼんやりと行手に浮んでゐる、さうして背後のさびしい往来では、
犬のほそながい尻尾の先が地べたの上をひきずつて居る。ああ、どこまでも、どこまでも、
この見もしらぬ犬が私のあとをついてくる、
きたならしい地べたを這ひまはつて、わたしの背後で後足をひきずつてゐる病気の犬だ、
とほく、ながく、かなしげにおびえながら、
さびしい空の月に向つて遠白く吠えるふしあはせの犬のかげだ。──『見しらぬ犬』
また、『月に吠える』の詩集全体を通じて、萩原は都市生活の中で感じる孤独や疎外感を繰り返し描いています。『地面の底の病気の顔』では、地面の底に現れる病人の顔が、萩原の内面の病みや孤独を象徴しています。
地面の底に顔があらはれ、
さみしい病人の顔があらはれ。地面の底のくらやみに、
うらうら草の茎が萌えそめ、
鼠の巣が萌えそめ、
巣にこんがらかつてゐる、
かずしれぬ髪の毛がふるえ出し、
冬至のころの、
さびしい病気の地面から、
ほそい青竹の根が生えそめ、
生えそめ、
それがじつにあはれふかくみえ、
けぶれるごとくに視え、
じつに、じつに、あはれふかげに視え。地面の底のくらやみに、
さみしい病人の顔があらはれ。──『地面の底の病気の顔』
これらの詩に見られる表現は、萩原の内面の葛藤や孤独感を強く反映しており、詩が単なる感情の発露ではなく、深い自己探求の結果であることを示しています。萩原は詩を通して、自身の孤独や不安を直視し、それらを詩的な表現に昇華することで、自らの存在意義を探求し続けていたのです。
『月に吠える』は、萩原朔太郎が都市生活における孤独や内面の絶望を鋭く捉え、その表現を通じて日本の近代詩に新たな地平を切り開いた作品集であり、彼の代表作として今日まで高く評価されています。
『竹』
『竹』は、萩原朔太郎が詩集『月に吠える』の中で発表した詩の一つであり、彼の作品の中でも特に独特な存在感を持つ詩です。この詩は、竹という身近な自然物を題材にしながらも、その奥に潜む深い哲学的な意味や人生観を描き出しています。朔太郎は、竹の成長や形状を通じて、人間の生き方や感情の動き、そして自然との関わりを詩的に表現しました。
『竹』は、竹のしなやかさや強さ、またその美しさに対する讃歌でありながら、一方で朔太郎自身の孤独や葛藤をも映し出しています。竹の姿が、時に人間の持つ内面的な強さやしなやかさを象徴していると解釈されることもあり、詩全体に漂う静かな力強さが特徴です。また、竹が風に揺れる様子は、外的な影響に左右されながらも自分自身を保ち続ける人間の姿を思わせます。
この詩は、形式的には口語自由詩として書かれており、定型に縛られない自由な表現が魅力です。リズムや音の響きを重視しながらも、内容的には深い洞察を含んでおり、読者に対して多層的な意味を感じさせます。竹というシンプルなモチーフを通じて、朔太郎は人間の存在や自然との調和を詩的に語りかけます。
ますぐなるもの地面に生え、
するどき青きもの地面に生え、
凍れる冬をつらぬきて、
そのみどり葉光る朝の空路に、
なみだたれ、
なみだをたれ、
いまはや懺悔をはれる肩の上より、
けぶれる竹の根はひろごり、
するどき青きもの地面に生え。──『竹』
『竹』の中で描かれる竹は、単なる自然の一部としてではなく、朔太郎にとって人生の象徴でもあります。竹の真っ直ぐな成長や節々の特徴は、人間が生きる上での節目や困難を表しているとも考えられます。竹の持つしなやかさと強靭さは、人生の試練に直面してもなお立ち続ける人間の精神を表しているのです。
光る地面に竹が生え、
青竹が生え、
地下には竹の根が生え、
根がしだいにほそらみ、
根の先より繊毛が生え、
かすかにけぶる繊毛が生え、
かすかにふるえ。かたき地面に竹が生え、
地上にするどく竹が生え、
まつしぐらに竹が生え、
凍れる節節りんりんと、
青空のもとに竹が生え、
竹、竹、竹が生え。──『竹』
また、朔太郎は竹を通して自然の美しさや儚さ、そしてその中で生きる人間の小ささをも描いています。竹が風に揺れ、雨に打たれてもその美しさを失わないように、人間もまた困難な状況の中でも自身の価値や美しさを保つべきだというメッセージが込められているともいえます。
現代においても、萩原朔太郎の『竹』は多くの人に読まれ、その深い意味が語り継がれています。彼の詩は教科書にも掲載されており、文学教育の中で触れる機会も多いです。また、詩の中で示される自然との関係性や人間の在り方についての考察は、現代の環境問題や人間関係の在り方にも通じるものがあり、その普遍的なメッセージは今なお多くの人々に響いています。
『青猫』
萩原朔太郎の詩集『青猫』(あおねこ)は、1923年に発表された作品であり、『月に吠える』に続く彼の第二詩集です。この詩集では、萩原の独特な感性がさらに深まり、幻想的で象徴的な表現が多く見られます。都市生活の中で感じる孤独感や疎外感、内面の葛藤が詩的に描かれており、朔太郎の内なる世界が色彩や音、風景を通じて視覚的・聴覚的に表現されています。
詩集のタイトルに使われている「青」という色は、朔太郎にとって冷たさや孤独、静けさを象徴しており、彼は自身の感情を動物や風景に託して表現しています。朔太郎は『青猫』の序文で、自身の詩の本質について述べています。
私は感覺に醉ひ得る人間でない。私の眞に歌はうとする者は別である。それはあの艶めかしい一つの情緒――春の夜に聽く横笛の音――である。それは感覺でない、激情でない、興奮でない、ただ靜かに靈魂の影をながれる雲の郷愁である。遠い遠い實在への涙ぐましいあこがれである。
詩を通して伝えたいのは、感覚や激情ではなく、静かに流れる魂の郷愁であると述べています。たとえば、『青猫』という詩では、孤独な存在を象徴する青い猫が登場します。
この美しい都會を愛するのはよいことだ
この美しい都會の建築を愛するのはよいことだ
すべてのやさしい女性をもとめるために
すべての高貴な生活をもとめるために
この都にきて賑やかな街路を通るのはよいことだ
街路にそうて立つ櫻の竝木[#「竝木」は底本では「並木」]
そこにも無數の雀がさへづつてゐるではないか。ああ このおほきな都會の夜にねむれるものは
ただ一疋の青い猫のかげだ
かなしい人類の歴史を語る猫のかげだ
われの求めてやまざる幸福の青い影だ。
いかならん影をもとめて
みぞれふる日にもわれは東京を戀しと思ひしに
そこの裏町の壁にさむくもたれてゐる
このひとのごとき乞食はなにの夢を夢みて居るのか。──『青猫』
また、『青猫』の詩集全体を通して、朔太郎の詩に対する考え方も詳しく述べられています。『自由詩のリズムに就て』では、「詩は何よりもまづ音樂でなければならない」といった信条を持ち、詩の音楽性について深く考察しています。
我我の詩では、音韻が平仄や語格のために選定されない。さうでなく、我我は詩想それ自身の抑揚のために音韻を使用する。
──『自由詩のリズムに就て』
朔太郎は、詩の音楽性を形式的なリズムではなく、内在する感情や旋律として捉えていることがわかります。
これらの詩や論考に見られる表現は、朔太郎の内面の葛藤や孤独感を強く反映しており、詩が単なる感情の発露ではなく、深い自己探求の結果であることを示しています。朔太郎は詩を通して、自身の孤独や不安を直視し、それらを詩的な表現に昇華することで、自らの存在意義を探求し続けていたのです。
『青猫』は、萩原朔太郎の詩の世界をより深く掘り下げ、彼の詩的な感性や哲学を余すところなく伝える作品となっています。詩集を通して、朔太郎の詩に対する独自の視点と、詩を通じた内なる感情の表現が繊細に描かれており、今日まで高く評価されています。
『猫町』
『猫町』(ねこまち)は、萩原朔太郎が1926年に発表した詩的散文で、幻想的な物語の中に朔太郎の詩的な感性が詰まった作品です。この作品では、朔太郎が夢の中で訪れた「猫町」という架空の町を舞台に、現実と幻想の狭間で揺れる心情を描いています。猫は朔太郎にとって特別な存在であり、その姿を通じて孤独や神秘、そして不安感を表現しています。
『猫町』では、猫が象徴するものとして、自身の内面の迷いや都市生活の喧騒からの逃避がテーマとなっており、読者に対して独特な世界観を提供しています。猫たちが支配する町で、朔太郎は人間の存在や生きることの意味を問い続けます。この作品は詩的な表現だけでなく、物語としても楽しめる構造となっており、朔太郎の創造力の豊かさを感じさせます。
町には何の変化もなかった。往来は相変らず雑鬧して、静かに音もなく、典雅な人々が歩いていた。どこかで遠く、胡弓
をこするような低い音が、悲しく連続して聴えていた。それは大地震の来る一瞬前に、平常と少しも変らない町の様子を、どこかで一人が、不思議に怪しみながら見ているような、おそろしい不安を内容した予感であった。今、ちょっとしたはずみで一人が倒れる。そして構成された調和が破れ、町全体が混乱の中に陥入ってしまう。──『猫町』
朔太郎はこの作品の中で、夢と現実、幻想と日常の境界を巧みに描き出しています。猫たちの町が一瞬で現実の田舎町へと変わる様子や、自身が見たものが幻影だったのか、現実だったのかという疑問は、読者を深く考えさせる要素となっています。
私の生きた知覚は、既に十数年を経た今日でさえも、なおその恐ろしい印象を再現して、まざまざとすぐ眼の前に、はっきり見ることができるのである。
──『猫町』
萩原朔太郎の『猫町』は、単なる幻想文学の域を超え、彼の内なる世界や詩的感性を豊かに反映しています。猫という存在を通じて、人間の孤独や不安を表現し、またその裏側に潜む人間の本質や存在意義を問いかけています。朔太郎にとって、猫は単なる動物ではなく、彼の詩的探求において重要な役割を果たす存在だったのです。
『こころ』
萩原朔太郎の詩『こころ』は、『純情小曲集』(じゅんじょうしょうきょくしゅう)収録の作品です。彼の詩作の中でも特に人気の高い作品で、人間の内面の感情や繊細な心の動きを描いています。この詩は、朔太郎が感じた人生の儚さや人間関係の複雑さを繊細な言葉で表現しており、読む人に深い共感を呼び起こします。
『こころ』では、心という見えない存在に対する畏敬や探求が描かれており、朔太郎が感じた孤独や不安、喜びなどの感情がストレートに伝わってきます。詩の中で用いられる言葉は平易でありながらも、その裏に隠された深い意味を感じさせる構造になっています。
こころをばなににたとへん
こころはあぢさゐの花
ももいろに咲く日はあれど
うすむらさきの思ひ出ばかりはせんなくて。こころはまた夕闇の園生のふきあげ
音なき音のあゆむひびきに
こころはひとつによりて悲しめども
かなしめどもあるかひなしや
ああこのこころをばなににたとへん。こころは二人の旅びと
されど道づれのたえて物言ふことなければ
わがこころはいつもかくさびしきなり。──『こころ』
この詩の描写には、朔太郎が人間の内面に抱く深い洞察と感受性が表れています。『こころ』は、人間の感情の儚さと、それがもたらす孤独感を巧みに表現しており、心という見えない存在の不確かさを詩的に探求しています。萩原朔太郎の詩は、日常の言葉でありながらも、その背後にある複雑な心情を浮かび上がらせ、読者に深い思索を促します。
次のセクションでは、萩原朔太郎と室生犀星の友情や詩からの旅立ちについて深掘りしていきます。朔太郎が犀星に寄せた思いとともに、詩に対する姿勢の変化や、それぞれの詩人としての道がどのように分岐していったのかを見ていきましょう。
萩原朔太郎と室生犀星のエピソード
萩原朔太郎と室生犀星(むろう さいせい)の関係は、詩作を通じて深い友情を育んだことで知られています。朔太郎は室生犀星の詩的才能を高く評価し、互いに刺激し合いながら詩作に励んだというエピソードがあります。しかし、室生犀星が詩に別れを告げて小説や随筆の世界へ移行したことは、朔太郎にとって大きな影響を与えました。
先に詩集「鐵集」で、これが最後の詩集であると序文した室生君は、いよいよ雜誌に公開して詩への告別を宣言した。感情詩社の昔から、僕と手をたづさへて詩壇に出て、最初の出發から今日まで、唯一の詩友として同伴して來た室生君が、最後の捨臺詞を殘して告別したのは、僕にとつて心寂しく、跡に一人殘された旅の秋風が身にしみて來る。
(中略)
室生君の「詩と告別する」を讀んで、僕は蒲原有明氏の言葉を考へ、當時の僕の感慨を、新しくまた繰返して感慨した。詩を必要としなくなつた室生君は、日本の風土氣候にすつかり調和し、身邊に樂しく住心地の好い家郷を持つた幸福人である。
(中略)
それゆゑ僕には「詩」は止められない。たとへ一篇の詩も書けずにゐても、詩と告別しては生きられない。なぜなら僕には、室生君の如くそれに代る別のポエム、即ち俳句や隨筆がないからである。僕の世界にある文學は、詩とエッセイの外に何物もない。そしてこれは二つ共、日本の風土氣候に合はないのである。
──『詩に告別した室生犀星君へ』
朔太郎の言葉からもわかるように、彼にとって詩は単なる表現手段ではなく、自身の存在そのものであり、詩と離れることは自身の生き方を否定することに等しいものでした。室生犀星の決断に対する朔太郎の複雑な感情は、二人の深い友情と詩への情熱を象徴しています。
次のセクションでは、萩原朔太郎にちなんだ賞や記念館について紹介し、彼の遺産がどのように現在も受け継がれ、詩の世界に影響を与えているのかを見ていきましょう。
萩原朔太郎の影響と遺産
萩原朔太郎賞とその意義
萩原朔太郎賞は、萩原朔太郎の業績を称え、現代詩の振興を目的として設立された文学賞です。この賞は、詩の分野において優れた業績を挙げた詩人に贈られ、詩の新しい表現を追求する詩人たちの励みとなっています。賞の選考基準には、独創的な表現や新しい詩のスタイルの開拓など、萩原朔太郎が生涯を通じて追求した詩の革新が重視されています。
萩原朔太郎賞は、詩人の創作活動を支援するだけでなく、詩というジャンルの魅力を広く伝える役割も果たしています。朔太郎の詩が持つ革新性や感性は、現代の詩人たちにも影響を与え続けており、この賞を通じて新たな詩の可能性が探求される場が提供されています。
まとめ
萩原朔太郎は、日本近代詩の先駆者として、その独特な感性と革新的な表現で多くの人々に影響を与え続ける詩人です。彼の代表作である『月に吠える』や『青猫』、幻想的な散文詩『猫町』など、どの作品も朔太郎自身の内面の葛藤や孤独、自然とのつながりを深く描き出しています。彼の詩は、現実の厳しさや都市生活の疎外感を反映しながらも、幻想的な世界へと読者を導き、その中で新しい視点や感情の共鳴を生み出しています。
また、萩原朔太郎に関連する萩原朔太郎賞は、彼の詩の魅力を広め、次世代の詩人たちの創作活動を支援する役割を果たしています。記念館では彼の詩作の背景に触れることができ、賞を通じて彼の詩の精神が受け継がれています。
萩原朔太郎の詩が持つ普遍的な魅力は、彼が詩を通じて描いた人間の感情や存在の意味への問いかけにあります。彼の詩を読むことで、自分自身の心の奥深くを見つめ直し、言葉の力を感じることができるでしょう。詩に詳しくない方でも、朔太郎の詩の持つ美しさや深みを感じ取り、彼の世界に触れてみることで、詩の新たな楽しみ方を発見できるはずです。